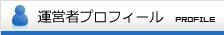平成26年10月6日付府共第631号をもって諮問された、男女共同参画社会基本法を踏まえた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的な考え方について、この程、その答申が行われました。今後、本答申を踏まえ第4次男女共同参画基本計画の策定を行うよう要請されています。
■男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的な考え方の概要
1.日本社会全体における状況の変化
人口減少が進む中、将来にわたって活力ある日本社会を維持するには、持続可能な地域社会を構築する必要がある。人口減少の問題は地域によって状況が異なっており、女性の活躍をめぐる状況や住民の意識も地域によって様々であることから、地域の実情に応じた取組が重要となっている。
2.女性をめぐる状況の変化
(ア)政策・方針決定過程への女性の参画
政府は、12 年前の平成15 年6 月、「社会のあらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」との目標を掲げ、取組を進めてきたが、今後、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要な目標であることから、これを社会全体で共有するとともに、現在の機運の高まりをチャンスととらえ、女性参画拡大の動きを更に加速していく必要がある。
(イ)М字カーブ問題と働き方の二極化
働く女性が増加する中で、第一子出産を機に、特に非正規雇用の女性の離職率が高い実態があることから、約6割の女性が離職するなど、女性の労働力率が子育て等を理由に30歳代で低下する状況は変わらない。また、正規雇用と非正規雇用という、いわゆる「働き方の二極化」への対応もM字カーブ問題と関連する重要な課題である。
(ウ)女性のライフスタイルや世帯構造の変化
男女の多様な生き方を可能とする社会システムへの転換が求められている。一方、晩婚化・未婚化や高齢者人口の増加による単身世帯、離婚によるひとり親世帯が増加しており、特に女性については、出産・育児・介護等による就業の中断や非正規雇用が多いことなどを背景として、貧困等生活上の困難に陥りやすい状況にあることが指摘されている。
3.男性の仕事と生活を取り巻く状況
依然として残る「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な性別役割分担意識、男女の能力や適性に関する固定的な見方や様々な社会制度・慣行がある。特に、長時間労働は、子育て・家事・介護等への男性の主体的な参画を困難にし、結果として女性が仕事と生活を両立することを難しくしていると同時に、自己啓発や地域コミュニティへの参加、本人の健康保持などを含めた、男性自身の仕事と生活の調和の実現も阻害する要因になっている。このため、男性が置かれている現状の労働環境等について、見直していくことが必要である。
4.東日本大震災の経験から得た教訓
東日本大震災では、被災地において、救助・救援、医療、消火活動及び復旧・復興等の担い手として、多くの女性が活躍した。一方で、物資の備蓄・提供や避難所の運営等において女性の視点に立った対応が十分ではなかったなど、様々な課題が明らかになった。それらの経験から、そもそも防災・復興における政策・方針決定過程への女性の参画が不可欠であること、災害対応における男女共同参画の視点が重要であることや、それらの実現のためには、多様な主体による平時からの連携が重要であることが改めて認識された。
5.女性に対する暴力をめぐる状況
配偶者等からの暴力、性犯罪等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。また、近年、SNSなどインターネット上の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、女性に対する暴力は多様化しており、そうした新たな形の暴力に対しても迅速かつ的確に対応していく必要がある。
6.国際社会への積極的な貢献の重要性
国連では、貧困の撲滅と持続可能な開発の実現に向けて、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を策定し、持続可能な開発の実現のための取組を開始した。男女共同参画、女性のエンパワーメント並びに女性及び女児の人権は、その取組の中心的な課題の一つとなっている。こうした新たな国際的な潮流や様々な国際会議における議論の進展を踏まえるとともに、女子差別撤廃条約等の積極的遵守の観点からも、幅広い年齢層、多様な主体と協働しつつ、国内における国際的な協調に向けた取組やODA等を通じた国際的な取組への積極的な貢献を進めていく必要がある。