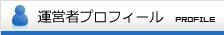会社を守る就業規則の要件として考えられる主なものは・・・?
就業規則の内容を変更する場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなくてはなりません。
就業規則の法的性格について最高裁は以下のように判断しています。
就業規則についての書籍もたくさんありますし、最近はインターネットでモデルとなる基本的なひな形サンプルも入手できますので、会社によってはこれらを利用して新規作成しているところもあるでしょう。ほとんどの会社には就業規則があるので、他社の就業規則を真似している部分もあるかもしれまんね。
基本的なことですが、就業規則が無いと社員に残業させることができません。
就業規則で残業について明記されていて、かつ、36協定を労基署に届け出ていることが必要です。
社員数10人未満で就業規則が無い会社の場合には、個々人との労働契約書に残業についての記述がしっかりと書いてあれば大丈夫です。今は10人未満でも将来社員が増えてきたときのために就業規則を作成しておきましょう。
本社と支店で同一の就業規則である場合には、本社で一括して届出することが認められています。内容が少しでも違う場合にはNGですが。
- 事業所の数の部数を届け出る
- それぞれの事業所においてその事業所の過半数代表者の意見書を添付
- 各事業所の名称・住所・管轄労基署名の一覧表を添付
以上を満たして、本社所在地を管轄している労基署へ一括して就業規則を届け出ることができます。
常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を作成または変更した場合には管轄する労基署に届けなければなりません。
就業規則を作成するとき、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意的記載事項をすべて第一条から最終条文までに含めて一本(一冊)の就業規則としてももちろん構わないのですが、たいていは、例えば、就業規則本編で、退職金に関する事項は「退職金規定」による・・・と書き、別途「退職金規定」を作成したりして、細かい部分を含む項目については別規定を作成します。
退職金規定、育児・介護休業規定、旅費規程、通勤規定、情報管理規定、などがあります。
規定のボリュームを考え、本則に入れ込むか、別にするか、就業規則を作成依頼した社労士と相談して決めましょう。
別規定も就業規則の一部であるので、労基署に提出する必要があります。別冊になっているので忘れないように要注意です。
もし、就業規則とある労働者と個別に結んだ労働契約に食い違う部分があった場合はどうなるのでしょうか。
作成した就業規則は従業員へ周知しないといけません。
常時10人以上の従業員をかかえている会社は就業規則を作成し、従業員過半数代表の意見書を添付して管轄労基署に届出なければなりませんが、作成したけど届出していなかった場合にこの就業規則の効力はどうなるのか・・。
労基署に届け出るのは、その会社がきちんと就業規則というルールブックを作って、従業員との労使関係を円滑にしている、ということを労基署が確認したいためです。
ということで、たとえ労基署に届け出るのを怠っていたとしても、未届については罰がありえますが、その就業規則自体が無効になるわけではありません。ただし、就業規則の従業員への周知は必要です。
就業規則とは、「守り」のツールといえます。就業規則を改定しても、大きく営業利益が伸びたり、従業員のモチベーションがアップすることはないでしょう。
新たにパートタイマーの従業員を雇った場合、既存の就業規則が正社員だけを対象にしているものである場合、新規にパートタイマー用の就業規則を作成しなければなりません。(全従業員が10人以上の場合)
就業規則を社員にとって不利益な内容に変更できるか、についてはまず下記の判例があります。
就業規則に書く内容としては下記のものがあります。
こちらでは就業規則に関する知識・情報を掲載します。
働いている人が9人以下の場合でも就業規則を作成しておく(労基署に提出はしなくていいですが)ことは社長・会社にとって非常に大きいメリットがありますので是非当事務所へご相談くださいませ。
10人未満の会社は就業規則の作成義務はなくても、労働者に対して労働条件通知書を作成し、交付する義務はあります。
ただ10人未満の会社だからといって就業規則を作成せずに、労働契約の締結の都度、それぞれの労働者に対して、個別に労働条件通知書を作成し、交付するというのは、むしろ手間がかかることでしょう。よって就業規則を作成しておくことが合理的です。
多くの労働者にとって仕事を失うことは恐怖であるため、会社から解雇されないようにして、弱い立場に立っているという状況です。それを労働基準法によって、会社が守るべき労働条件の最低基準を示し、これに違反すると会社に罰則を科すことにより、労働者を保護しています。
適切な就業規則を定めると下記のような効果が得られるでしょう。
就業規則とは、労働時間や賃金といった労働条件や職場の規律を文書化した、使用者と労働者との間のルールブックです。