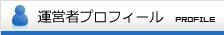こちらでは社会保険に関する知識・情報を掲載します。
10月10日、日本政府とルクセンブルク政府との間で、社会保険料の二重払い等の問題解消をするための「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」の署名が行われました。わが国は、これまで15ヶ国との間で社会保障協定を発効させており、他の諸国とも順次交渉を進めています。
厚生労働者は、平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える雇用・労働、年金、医療保険、介護保険関係等についてその概要等をまとめて公表しています。
次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した人は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。なお、当該保険料免除の対象は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者となります。
8月23日、日本政府とハンガリー政府との間で、社会保険料の二重払い等の問題解消をするための「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」の署名が行われました。わが国は、これまで14ヶ国との間で社会保障協定を発効させており、他の諸国とも順次交渉を進めています。
技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目的として、平成24年5月に建設業法施工規則が改正されました。
これはとても重要な改正で、建設業に関わる方は熟読ください。
- 1平成24年7月より、保険未加入企業に対して、経営事項審査の評価点が厳しくなります。
具体的には、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入だと各40点減点されます。
3つとも未加入だと120点減点となります。
(今までは全部未加入で60点減点でしたので2倍になりました!)
- 2平成24年11月より、許可申請書に保険加入状況がわかる書面を添付する必要があります。
建設業の許可・更新時に保険加入状況を書面を提出。国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては加入指導を実施。
- 3平成24年11月より、施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要になります。
施工体制台帳に特定建設業者および下請会社の保険加入状況を記載。下請会社は再下請会社の保険加入状況を特定建設業者に通知。国・都道府県の建設業担当部 局は営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳の確認を行い、元請企業による下請企業への指導 状況の確認を実施。
今年、来年あたりは保険加入状況を役所にじっくり見られることでしょう。社会保険は高いですが、ほっといて立入検査が入った場合、面倒なことになります。この際きちんと加入すべきでしょう。
ということで、建設業の経営者様、ご相談は、社会保険労務士ながや事務所へどうぞ。
会社を退職したときの医療保険・健康保険は
- 1健康保険の任意継続被保険者
- 2国民健康保険の被保険者
- 3家族の健康保険の被扶養者
から選ぶことになります。なお、「国民」が頭につく国民健康保険は、簡単に言うと、市町村が運営する健康保険で、自営業、フリーターの人のためにあるのです。会社員、お勤めされている方は「国民」がつかない健康保険です。「国民」がつくかつかないかで違いますので、使い分けてください。
1. 任意継続とは勤続2ヵ月以上の者が、現在の医療保険に継続して加入できる制度。継続可能期間は原則2年間。
私も都庁を辞めたとき、印西市の国民健康保険と比較して”任継”のほうが安かったので、コレを選択しました。
保険料は退職時の給与により決定されます。退職前の2倍相当額(会社と折半負担になっているのが全額自己負担となるため) こんなに高いの!と感じることでしょう。
2. 国民健康保険は住所地の市町村により保険料の額が異なります。前年の収入により決定。市町村により異なるため、各市町村窓口で試算してもらったりして1.の任継と比較検討すべきでしょう。
3. 被扶養者になるための一定の要件(所得制限等)があるので、人によっては3.を選択することができないかもしれません。
被扶養者の範囲は・・・
- 1被保険者によって生計を維持されている配偶者(内縁関係含む)
- 2被保険者によって生計を維持されている直系尊属
- 3被保険者によって生計を維持されている子、孫、弟妹
- 4同居し、かつ被保険者によって生計を維持されている三親等内の親族
- 5同居し、かつ被保険者によって生計を維持されている内縁関係にある配偶者の父母および子
(兄姉は3.ではなく、4.であることに注意)
生計維持とは・・・
- 被保険者と同居の場合⇒被扶養者の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
- 被保険者と別居の場合⇒被扶養者の年収が130万円未満かつ被保険者の仕送り額より少ないこと
健康保険対象外となる主なケースは・・・
- 業務上・通勤途上の怪我や病気
仕事中や通勤途上で事故にあったり病気になった場合は、労災保険の対象となりますので、健康保険は受給できません。
- 故意の犯罪行為により、または故意に事故を生じさせて怪我をしたとき
自殺未遂の後に治療が必要な場合は給付制限に該当し、治療費は全額自己負担となります。
- 正常な妊娠・出産
正常な妊娠による定期検診、分娩、入院には健康保険がききませんが、子宮外妊娠や帝王切開などが必要な異常分娩の場合には、健康保険が適用されます。
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容を目的とするもの
- 第三者行為での怪我や病気
etc
介護保険において、介護保険のサービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の寝たきりや痴呆になった要介護者です。
40歳から64歳までの第2号被保険者は「加齢に伴う特定の疾病に起因する介護」に限るとされています。具体的には「要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」とされ、以下の15疾患が挙げられています。
- 1筋萎縮性側索硬化症
- 2後縦靭帯骨化症
- 3骨折を伴う骨粗鬆症
- 4シャイ・ドレーガー症候群
- 5初老期における痴呆
- 6脊髄小脳変性症
- 7脊柱管今狭窄症
- 8早老症
- 9糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 10脳血管疾患
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性間接リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者が、介護保険によるサービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度について要介護(要支援)認定を保険者である市町村から受ける必要があります。
要介護認定は、市町村職員等による訪問調査によって得られた情報および主治医の意見書に基づき、市町村に設置される「介護認定審査会」で全国統一の基準に基づき、公平・公正に行われることになっています。
実際に被保険者の自宅へ職員・専門家が来て、ヒアリングをして、1か月以内には要介護、要支援またはいずれにも該当しない、の判定が出ることになります。
介護保険には第1号被保険者(65歳以上の者)は、区市町村において徴収し、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)は、加入している健康保険保険者が健康保険の保険料に併せて徴収します。
第1号被保険者については、特別徴収と普通徴収の2通りがあり、特別徴収というのは、老齢または退職を支給事由とする年金給付から介護保険料を天引きする方法で、天引きした保険料を年金保険者が市町村に納付します。普通徴収というのは、市町村において第1号被保険者の各世帯主に、直接、納付書を送付して金融機関等を通じて、徴収する方法です。
第2号被保険者については給料からさっぴかれるということになります。
毎年7月1日現在に在籍する全被保険者の標準報酬月額について定期的に見直しを行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを定時決定といい、手順としては被保険者報酬月額算定基礎届に、被保険者の4月・5月・6月の各月に支払われた報酬と3ヶ月の平均額を、総括表に所定の事項を記入して、7月1日から10日までに社会保険事務所に提出します。
報酬にはもちろん残業代も含まれますので、4・5・6月に沢山残業すると9月以降の保険料が上がります。よって保険料を抑制したいのならこの3か月間はあまり働かず、他の月に残業するとよいでしょう。こんな調整は難しいと思いますが・・。
4・5・6月の給料で健康保険料が決まっているということは覚えましょう。
パートタイマーを健康保険に入れなければならないかどうかは、一般的に勤務時間と勤務日数がそれぞれ社員の4分の3以上であるかを目安として判断しますが、法律上の基準があるわけではありません。
労働時間としては、1日の所定労働時間が社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。たとえば社員の所定労働時間が1日8時間とすれば、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わる場合は1週間を平均して判断します。
勤務日数としては、1ヵ月の勤務日数が社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
上記はあくまでも目安で、これに該当しない場合でも、就労の形態や内容を総合的に考えて常用的な使用関係が認められた場合は被保険者となります。管轄の社会保険事務所や健康保険組合によっても、細部の基準が違う場合がありますので確認してみるとよいでしょう。
平成24年度の健康保険料率は
| 東京都 | 9.97% |
| 神奈川県 | 9.98% |
| 千葉県 | 9.93% |
| 埼玉県 | 9.94% |
| 茨城県 | 9.93% |
保険料率は都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映したものとなっています。
40歳から64歳までの方(介護保険2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.55%)が加わります。
平成24年度の健康保険料額を掲載します。
他の都道府県については
高額な外来診療についても窓口負担を軽減するための仕組みが導入されます。(平成24年4月1日〜)
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(高額療養費の外来現物給付化)が導入されます。
高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途お支払いが必要です。
限度額適用認定証を利用する場合の流れ
限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出してください
限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安、1週間程度)
医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します
同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります
この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
健康保険限度額適用認定申請書は下記ページの【4】です。
70歳未満の高額療養費の自己負担限度額は
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
(多数該当83,400円)
一般(上位所得者、低所得者以外)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
低所得者(被保険者が市町村民税非課税等)
35,400円
(多数該当24,600円)
※多数該当とは・・・療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合、4ヶ月目から自己負担限度額が軽減されます。
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後につくられた薬です。先発医薬品と同等と国から認められた上で発売されている安価な薬であり、薬代の負担軽減につながります。
(ジェネリック、generic = 一般的であること。共通していること。)
- 薬代が安くなります
先発医薬品の開発が10〜15年、数百億もの投資が必要といわれるのに対して、ジェネリック医薬品の開発期間は3年ほどと短く、また研究開発費用も当然低くなります。これらのコストを安く抑えることができるので、それが薬価にも反映されることになります。薬代として3割以上、中には5割以上安くなる薬もあります。
- 効き目や安全性は同じ
ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ主成分を使い、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認されたお薬です。医薬品は薬事法によりさまざまな規制が定められています。ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ規制のもとで開発・製造・販売されていますので、品質に違いは無いと考えられています。
- ジェネリック医薬品を利用するには
ジェネリック医薬品は医師による処方せんが必要ですので、まずは医師・薬剤師にご相談ください。ただし、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。使用できる病気(効能)が異なる場合や、在庫がない場合など切り替えることができない場合があります。
ジェネリック医薬品についての情報サイト
(日本ジェネリック医薬品学会)
健康保険は、被用者の医療保険の中心的な制度です。一般職域に常時使用される労働者を被保険者とし、労働者の業務外の事由による疾病・負傷・死亡または出産と、その被扶養者の疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行うことによって、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
また、いわゆる日雇労働者については、日雇特例被保険者とされ、被保険者と同様の保険給付が行われます。
国民健康保険は、農山漁村の住民や都市の商工業自営業者等、被用者以外の地域住民を被保険者とし、その疾病・負傷・出産・死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。国民健康保険においては、被扶養者という概念はなく、原則としてすべて被保険者として取り扱われます。
健康保険等の被用者医療保険の被保険者・組合員およびその被扶養者は、その資格を喪失すると原則として住所地の市町村が行う国民健康保険の被保険者となりますが、このうち一定の者については「任意継続被保険者」とされます。任意継続被保険者制度といわれ資格喪失日の前日までに被用者医療保険に継続して2か月以上の被保険者期間があった場合に退職後2年間は今まで加入していた健康保険制度が利用できるというものです。
医者にかかったときに窓口で支払う料金(健康保険による一部負担金)についてですが
- 70歳未満の被保険者はかかった医療費の3割を
- 70歳以上75歳未満の被保険者は2割 (ただし、平成25年3月31日までは1割)
となっています。平成25年4月1日以降70歳以上75歳未満の方はご注意ください。
なお、75歳以上の方は健康保険の被保険者ではありません。75歳になると強制的にけんぽから脱退です。後期高齢者医療制度の被保険者となり、窓口負担は1割です。
後期高齢者とは75歳以上の方です。75歳になると、健康保険または国民健康保険からは脱退し、後期高齢者医療制度に自動的に移行します。手続きは必要ありません。65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は申請し後期高齢者医療の被保険者となることができます。
一定の障害とは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
- 音声・言語・そしゃく機能障害
3.療育手帳A1・A2をお持ちの方
4.障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
5.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
後期高齢者医療制度は各都道府県に設置された広域連合が運営します。その都道府県内のすべての市町村がその広域連合に属します。⇒各都道府県後期高齢者医療広域連合 (一番下にあります)
保険料の納付については、公的年金の支給額が年額18万円以上の方は、2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が引き落とされます。これを特別徴収といいます。年18万ですからほとんどの方は特別徴収されます。
ただし、年度途中での転入や75歳になったばかりの方などは、一定期間特別徴収とはなりません。納付書が自宅に届くのでそれを金融機関に持参して納付します。これを普通徴収といいます。
で、どのくらいの保険料となるかというと、千葉県の24年度(25年度も同じ。2か年度ごとに見直し)の保険料は、均等割額=37,400円・・・①、所得割額=(前年総所得−33万円)×7.29%・・・②で、①と②の合算額が年間の保険料額となります。なお、老齢○○年金も所得に入ります。
たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金合わせて年間233万円あり、これ以外は収入がないとすると、②は200万円×7.29%=145,800円となり、①+②=183,200円です。ということは年金233万円からこれを引くし、所得税もかかるので200万円を下回ってしまうでしょう。
病院の窓口での自己負担割合は1割です。診察が終わって、お金を支払うときに、「1,000円でーす」と言われたら、トータル1万円かかっているということです。
子ども手当と児童手当について整理しておきましょう。
子ども手当とは政治的な理由で平成22年度に創設されましたが、平成23年度までの2か年度で廃止されました。よって今後は子ども手当という名称は登場しません。
平成24年度からは以前からあった児童手当法の一部を改正する法律に基づき、児童手当が支給されます。つまり、名称が変わりますが、子供を持つ親などへの手当は継続されます。
児童手当の支給額は
- 3歳未満・・・月額15,000円
- 3歳以上小学校終了前・・・月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
- 中学生・・・月額10,000円
ただし、平成24年6月分から所得制限が適用され、制限額以上である場合は月額5,000円となります。
育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。
その一部の規定とは下記のとおりです。
- 介護休暇制度
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができる。
- 短時間勤務等の措置
事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。
短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ、介護費用の援助措置。
- 所定外労働の免除
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのため働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い報酬を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やケガで休んだ期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について会社から報酬が出ている場合はその分傷病手当金の支給額が調整されます。
支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
なお、国民健康保険、任意継続には傷病手当金はありません。
社員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる必要があるのに加入させていないとどうなるのでしょう。
確かに保険料の半額を労働者の給料から引かれるので、少しでも手取り額を減らしたくないということで、労働者から、入らなくてもいいよ、なんて言われることもあるかもしれませんね。
でも、万一ケガや病気で会社を休むことになった場合、健康保険に加入していれば傷病手当金が出ます。国民健康保険には傷病手当金はありません。
また、万一障害になってしまった場合には厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金が受給できるかもしれません。死亡保障として、遺族厚生年金もあります。
なお、年金事務所の調査によって、加入漏れの社員が発覚した場合には、最大2年前までさかのぼって保険料が徴収されます。保険料は労使折半なので、会社負担分だけでなく、社員にも負担してもらうことになりますが、とても言いづらいに違いありません・・。
普段健康な生活を送っていると社会保険の必要性はあまり感じないかもしれませんが、加入することで、会社も社員も安心できます。
後期高齢者医療制度についてですが、平成24年7月9日から外国人の方の資格取得要件が変わります。
住民基本台帳法の改正により高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、現在の資格取得要件である「一年を超える在留期間」が「3ヶ月を超える在留期間」に変更されます。
制度への加入は自動的に行われます。届出の必要はありません。